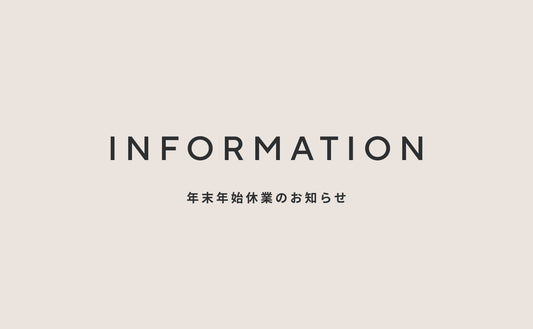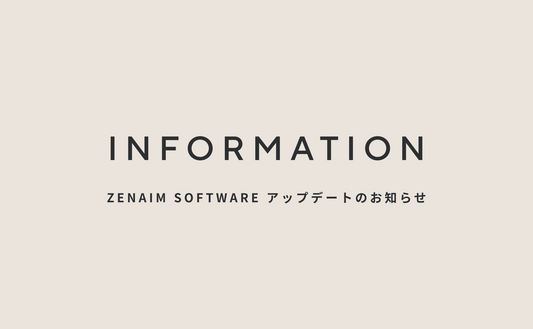ZENAIM INSIDE STORYは、ゲーミングギアブランド『ZENAIM』に携わるプロジェクトメンバーを通して、ブランドの魅力を伝えるコラム企画です。
フォーカスパーソン
西岡 知希(Kazuki Nishioka)
ZENAIM製品の立ち上げから品質保証までを支える西岡。品質管理部として、部品や工程の設計段階から介入し、「良品を安定して作り続けるための仕組みづくり」を担う。
かつては車載部品の品質保証を担当していた経験を持ち、その緻密な品質基準をゲーミングデバイスの世界へ持ち込んでいる。「プレイヤーがどんな環境で使っても同じパフォーマンスを出せるように」。そんな彼の現場へのまなざしが、ZENAIMの精密さを支えている。
組み付けの精度がキーボード全体の質感を左右する
インタビュアー:西岡さんがZENAIMのものづくりの中で、特にこだわっている点を教えてください。
西岡:我々の仕事って、ただ「良いものを作る」だけじゃないんですよ。大事なのは、良いものを安定して作り続けること。だから製造工程をつくり込むときも、「どうすれば同じ品質を保てるか。言い換えれば、全てのユーザーにZENAIMクオリティを届けられるか。」を常に意識しています。寸法の管理方法や、どの部品をどこまでチェックするか等、そういったルールを細かく設計段階で決めていきます。
インタビュアー:その“ルール設計”が、ZENAIMの品質を支えているんですね。
西岡:そう考えています。キーボードって、一見単純な構造に見えて、実は組み付けの精度が製品全体の質感を左右するんです。そしてプレイの精度にも直結します。コンマ1秒の世界で戦うプレイヤーにとって「忠実に反応するか」「違和感なく武器として手に馴染むか」は欠かせない要素です。だから、部品の誤差をどこまで許容できるか、問題が起きたときにどう検知するかを仕組みとして残す。そうやって、誰が作っても一定のZENAIMクオリティが実現できる状態を保つことは非常に重要です。

車載品質の思想を、ゲーミングデバイスへ
インタビュアー:西岡さんはこれまで、車載部品の品質保証を担当していた経験もあると伺いましたが、ZENAIMのものづくりに、その経験はどう活かされているんですか?
西岡:一番大きいのは、“品質基準を決める感覚”だと思います。車載って、命を預かる製品なんです。だからこそ、1ミリの誤差があったとしても、それが許容できる誤差だと保証する理由がある。その経験があるからこそ、ZENAIMでも「ここは譲れない」「この誤差はプレイに影響を及ぼさないから大丈夫だ」という判断をブレずにできるんです。
インタビュアー:車載とゲーミングでは全く違う世界のように見えますが、根底はつながっているんですね。
西岡:そうですね。ただし、ZENAIMの開発スピードは車載とは比べものにならないくらい速いんです。そんな中でも品質を落とさないために、工程を“最短で最適化”する工夫をしています。
100のステップがあるなら、品質を守るために必要な60を見極めて集中する。スピードの中で精度を保つことが、今の自分たちの挑戦です。
ZENAIMの製品は、作り手の想いの積み重ねでできている
インタビュアー:ZENAIM KEYBOARD2(TKL/mini)がリリースされてすでに多くの反響をいただいています。これからのZENAIMの開発について、どんな想いをお持ちですか?
西岡:キーボードの開発で得た学びは、今後のあらゆるZENAIMプロダクトに必ず生かされます。実際に、設計評価の仕方や試験項目の決め方は、チーム全体でブラッシュアップし続けています。「失敗を繰り返さないこと」も品質の一部だと思っていて。ひとつ前の挑戦を無駄にしない、それがユーザーの皆さんに良いプレイ体験を届ける我々の責任ですね。
インタビュアー:まさにZENAIMの品質を次へつなぐ役割ですね。
西岡:そうありたいですね。ZENAIMの製品って、スペックやデザインだけじゃなくて、作り手の想いの積み重ねでできているんです。ひとつひとつの試験、ひとつひとつのチェックに意味がある。ユーザーの手に届いた瞬間、「この製品は信頼できる」と感じてもらえるように、これからも一台一台の生産のクオリティを突き詰めていきたいです。
インタビュアー:今日はありがとうございました!西岡さんのお話を聞いて、ZENAIMの生産の裏側を知ることができました。
西岡:ありがとうございました。ZENAIMは今後、まだまだ進化していくブランドです。引き続き良いデバイス体験を届けられるよう、頑張っていきますので応援をよろしくお願いします。